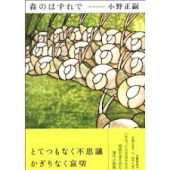
森のはずれで |
| 小野正嗣(著) |
| 文藝春秋 |
| ★★★★★ |
| 「妻が二人目の子供の出産のために実家に帰ったので、しばらく息子と二人きりで生活することになった」 と冒頭一行でアリバイが揃うこの小説、小野正嗣『森のはずれで』は、 糸の切れた凧のように抑制を欠いた数多のマジックリアリズムと一線を画し、マジックとリアリズムの極めて曖昧な境界に留まり続けている。 例えば「得体の知れない」片乳を出した老婆に「老婆はどことなく恥ずかしそうにうなずいた」を、 一羽のメンドリを攻撃する「仲間のメンドリたち」に「庭の一部が、白いうねりとなって、うごめいていた」を与える。 描写の対象への距離をいじるだけで、マジックもリアルにリアルもマジックになる、というより、 そもそもマジックもリアルもなくて、そこには描写しかなかったことに気付かされる。 U.U.
|
