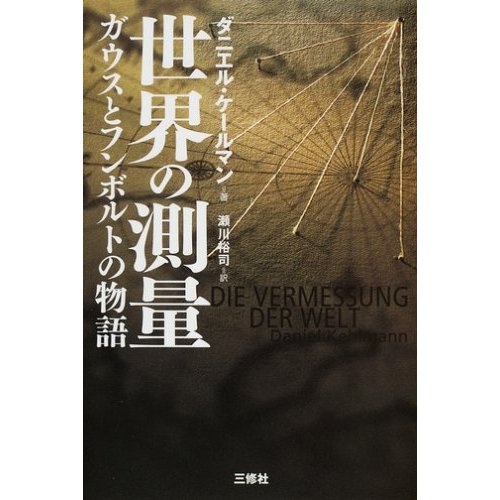
世界の測量 |
| ダニエル・ケールマン(著) 瀬川裕司(訳) |
| 三修社 |
| ★★★★☆ |
ダニエル・ケールマンのベストセラー『世界の測量 ガウスとフンボルトの物語』は、 「旅」に関する物語であり、ずっと家にいることさえ、場合によっては「旅」の一形式に過ぎないと提示する。 肉体は世界各地を自由に旅行しながらも、精神は甚だ硬直の嫌いがあるフンボルト像と、肉体は祖国から一歩も離れないが、 やけに風通しのいい精神を持つガウス像、彼らの体の自由と心の自由の対照を交互の章で語りながら、仕舞いには、
と、二対が見分けが付かないくらいに融合するこの物語は、 そもそも、肉体であろうと精神であろうと彼らの行為が「旅」であったことを示している……というよりも、 この小説において「旅」とは彼らの行為の隠喩なのである。 主人公であるフンボルト(1769-1859)とガウス(1777-1855)は、 ゲーテ(1749-1832)、ナポレオン(1769-1821)、ヘーゲル(1770-1831)、ベートーヴェン(1770-1827)などと同時代人であり、 カント(1724-1804)辺りが先鞭を付け、フローベール(1821-1880)辺りで早くも斜陽の兆しを見せる「独創性」の時代を生きた。 「独創性」という概念が確立され、無条件で顕揚された短くも幸福な時代であり、 実は彼らの「旅」とは、極短期間だけ人々に許された「天才」の所産に他ならない。 この小説は、ガウスの息子オイゲンがアメリカへ渡る場面で終わるのだが、 ナポレオン3世(1808-1873)と同時代人であるこのオイゲン(1811-1896)こそが我らの同時代人であり、 本人の素質とは無関係に「独創性」というものが揺らいで「凡庸」が発明された時代を生きている。 だからこそ、ガウスに始終罵倒されているオイゲンの姿に、われわれは胸を酷く締め付けられるのだ。 そもそも、「天才」たちだって最終章付近では如何にも惨めではないか……。しかし、この痛々しさは老衰の悲哀などでは毛頭なくて、 「独創性」神話自体の衰退に他ならず、老衰は寧ろ彼らにとって救いなのだ。 何しろ、オイゲン(=我々)ときたら、否応なしにその先の息苦しい時代をたっぷり生きることになる。 だから、オイゲンのアメリカ行きは間違っても「旅」ではないのであって、彼の行為は、物語を一切駆動しないだけでなく、 あっけらかんと終わらせてしまう他ない。 U.U.
特集:帰郷・再訪 |
