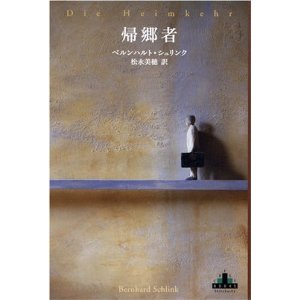
帰郷者 |
| ベルンハルト・シュリンク(著) 松永美穂(訳) |
| 新潮社 |
| ★★★★☆ |
| ベルンハルト・シュリンク『帰郷者』は、全篇にホメロスの『オデュッセイア』が縦糸のように織り込まれているのだが、 とりわけ、アイデンティティを変えて戦争責任を逃れ、アメリカで学者になっているド・バウアーの講義としての、『オデュッセイア』への言及に興味を覚える。 オデュッセウスは家へ帰ろうと努力しているのではなく、 (……)彼は自分の決心ではなく、神々の忠告に従って帰郷する。 (……)オデュッセウスは本当の意味で帰郷したわけではなかった。彼はすぐにまた旅立たなければいけない。 「訳者あとがき」によれば、「『帰郷者』に出てくるド・バウアーのモデルとして、 ドイツの書評はベルギー出身で戦時中に反ユダヤ的な発言をし、戦後アメリカに渡って脱構築批評で有名になった学者ポール・ド・マンの名を挙げている」とのことで、 訳者は「こうした人々の場合は『帰郷』ならぬ『棄郷』というべきかもしれない。 彼らは新天地を求め、過去と決別して新しい人生を歩み始めたのだった」と続けている。 しかし、この講義の場面から感じるのは、ド・バウアーは故郷を棄ててはおらず、寧ろそれに執着しており、ただ、故郷を想う度に、 常に「すぐにまた旅立たなければいけない」だけだということだ。 また、この「すぐにまた旅立たなければいけない」という「帰郷」に関する捉え方は、 ノヴァーリス『青い花』の「自分はこれから向かっていく世界からの長い遍歴を終え、いつかまた故国へもどってくるだろう、 つまり自分はそもそも故郷へ向かって旅をしているのだ、という気がしたのだ」という「旅立ち」に関する感慨と精確に対をなしている。 「旅立ち」⇔「帰郷」というこの循環は実は表裏一体なのではなかろうか? U.U.
特集:帰郷・再訪 |
